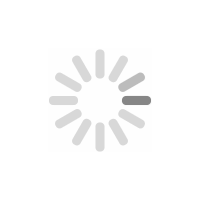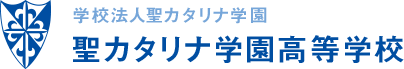- 校長の声
No.59 未来への声・過去への響き
■□■ No.59 未来への声・過去への響き■□■
前回、三つの俳句を並べました。
渡部勇毅君(看護科1年生)の句―「腹見せて消費期限の蝉が逝く」
芭蕉の句―「やがて死ぬけしきは見えず蝉の声」
私の駄句―「年も逝く逝くまでは鳴け蝉のごと」
その後、作家・平野啓一郎氏の「分人主義」という考え方が気になって氏の著書を読みかじっているうち、『ある男』という無愛想な(有島武郎の『或る女』を意識したような)タイトルの長編小説(単行本で351ページ)の終わり近く(343ページの最終行)、ドラマがクライマックスを迎えるところで、次の俳句に出くわしました。
「蛻(ぬけがら)にいかに響くか蝉の声」
句の作者は中学生。彼の言葉―「公園の桜の木に、蝉の蛻がひとつ、とまっていました。/(改行)木の上では、蝉がたくさん鳴いていました。/僕は、この蛻から飛んでいった蝉の声は、どれだろうかと耳を澄ましました。そして、残された蛻は、七年間も土の中で一緒だった自分の中身の声を、どんなふうに聞いているんだろうと想像しました。/蛻の背中のひび割れは、じっと見ていると、ヴァイオリンのサウンドホールみたいな感じがしました。そして、蛻全体が、楽器みたいに鳴り響いているように見えたので、僕は、この句を思いつきました。」
蝉の抜け殻は、今は「物」になっていても、ここでは、途切れない一つの命の、新しい鳴動の共鳴体と感受されています。
蝉において、「未来」へ向けて正に命懸けで「今」を鳴く声が抜け殻(「物」)へ響いているのではと感受したとき、鳴いている命の母胎だった抜け殻(「過去」)があってこその「今」なのだと、初めて「過去」という「もの」を発見できたのでしょう。
一つの年が逝っても、途切れることなく、次の年は続きます。一つの命が逝っても、類の存在は途切れません(地球環境が健在ならば)。「物」になっても「今」と共に生きる「もの」はあるとして、しかし、それも、「物」(「過去」)においては、自己の計らいの外のこと。
親と子がそう(『ある男』のテーマ)なら、教育(教師と生徒)もまた?
平野氏の著書は『ある男』も『私とは何か―「個人」から「分人」へ―』も本校図書館にあります。
写真は、高村光太郎の木彫作品「蝉」という「物」。そして、「未来」が見えつつある新校舎の現況と校長室内の「今」のお花です。
 |
 |
 |
 |
 |
 |
カテゴリー
月別アーカイブ
 2025年 (88)
2025年 (88) 2024年 (130)
2024年 (130) 2023年 (157)
2023年 (157) 2022年 (110)
2022年 (110) 2021年 (92)
2021年 (92) 2020年 (64)
2020年 (64) 2019年 (24)
2019年 (24) 2018年 (22)
2018年 (22)